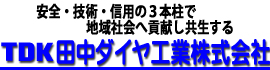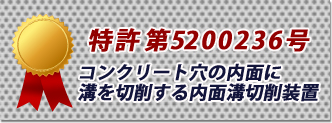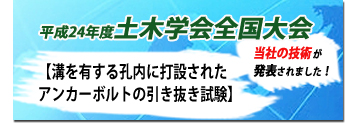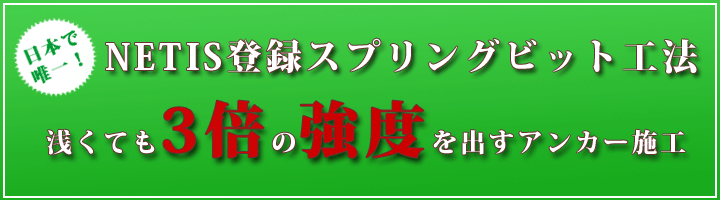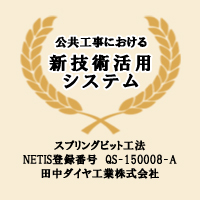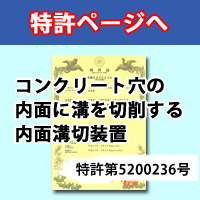- 2021/09/06
- 公共工事等における新技術活用システムのご案内
- 2017/08/31
- 2017年8月29日(火) ちば千産技術・新技術にて発表いたしました。
- 2017/08/31
- 2017年5月19日(金) 第4回新技術発表会in仙台 にて、発表いたしました。
- 2017/05/02
- 2017年4月28日(金) 建設新聞 東北に掲載いただきました。
- 2017/02/27
- 首都高速道路株式会社様において
- 2016/11/30
- 建通新聞社主催 浜離宮建設プラザにて講演
- 2016/11/30
- 帝国ホテル 孔雀の間にて講演
- 2016/07/01
- スプリングビット始動 160φ、125φも追加
- 2015/08/31
- 2015年7月13日にNETISに登録完了しました。
- 2015/03/11
- 積算資料 2015年 1月号に掲載されています。
- 2015/03/11
- 建築資材データベース 2015 掲載されました。
- 2015/03/11
- コアビット 意匠登録証 とっています。
- 2015/03/11
- コアキャッチャー 実用新案 とっています。
- 2014/12/15
- TDK 田中ダイヤ工業(株) 使用機器展示
- 2014/07/09
- 2014年7月4日 5日 幕張メッセ グランドフェア2014に出展しました。
- 2014/07/09
- 2014年7月7日(月) 株式会社 TCパワーラインより感謝状を受けました。
- 2014/04/02
- 建設工業調査会 ベース設計資料に掲載されました。
- 2014/01/20
- ニューテクノ今 第7回土木構造物の維持管理技術研究会
- 2014/01/20
- 東京大学研究会
- 2013/07/03
- 2013年7月3日付 建設通信新聞に「スプリングビット工法」開発版が掲載されました